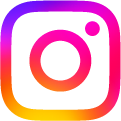税金マニュアル





不動産と税金。正しく知ることが、一番の節税。
税金マニュアル
税金のしくみを知り、不動産売買を安心に
不動産売買に伴う税務上の留意点と対策。


不動産取引に関わる7のTAX
TAX
1
印紙税
不動産の契約書作成時に納付する税金(国税)です。
工事請負契約書や売買契約書、住宅ローン契約書の作成の際には、契約書の記載金額に応じた収入印紙を貼って消印する方法によって印紙税を納めなければなりません。
印紙税の税額(平成18年4月1日現在)
| 契約書の記載金額 | 工事請負契約書 | 売買契約書 | 住宅ローン契約書 |
|---|---|---|---|
| 100万円超200万円以下 | 400円 | 2,000円 | 2,000円 |
| 200万円超300万円以下 | 1,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
| 300万円超500万円以下 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
| 500万円超1000万円以下 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| 1000万円超5000万円以下 | 15,000円 | 15,000円 | 20,000円 |
| 5000万円超1億円以下 | 45,000円 | 45,000円 | 60,000円 |
| 金額の記載のないもの | 200円 | 200円 | 200円 |
TAX
2
登録免許税
不動産を登記する際に納付する税金(国税)です。
不動産を登記する際には、「表示登記」を除いて、税金を納付しなければなりません。これを「登録免許税」といいます。不動産の保存登記、移転登記、抵当権設定登記等により第三者への対抗要件を備え、保護される利益に対して課税される税金です。納付方法は現金納付が原則ですが、登記所で現金を支払うわけではありません。国税の収納機関(日本銀行の本支店、国税の収納を行うその代理店および郵便局)に金銭で納付し、納付した領収書を登記の申請書に貼り付けて、登記所に提出するようになっています。(「登録免許税」の額に相当する印紙を登記申請書に貼り付けて提出することが認められるケースもあります。)
印紙税の税額(平成18年4月1日現在)
| 保存登記 | (建物)固定資産税評価額×0.15% ※1 |
|---|---|
| 移転登記 |
(建物)固定資産税評価額×0.3% ※1 (土地)固定資産税評価額×1% ※2 |
| 抵当権設定登記 |
債権額×0.1% ※1 【公庫・財形年金は非課税】 |
※2:平成20年3月31日まで
- ・新築住宅は、床面積が50m²以上(登記簿面積)
- ・中古住宅は、新築後20年(耐火構造の場合は25年)以内で床面積が50m²以上
- ・住宅専用家屋または住宅部分の床面積が9割以上の併用住宅
- ・自ら居住するための住宅であること
- ・新築または取得後1年以内の登記であること
固定資産税評価額とは
固定資産税の課税台帳登録価額(登記価額)のことです。 実際にかかった住宅建築費や土地の購入価額ではありません。 新築や増築、改築の場合は、まだ登録されていませんので、他の固定資産税台帳価額を基礎として、登記官が認定した価額になります。一般的に、建物は建物建築費の約5~7割、土地は取引価額の約7割程度といわれています。
債権額とは
融資金のことです。
TAX
3
贈与税
住宅を取得するとき、何ら対価(お金)を支払わずに無償で取得した場合、贈与を受けたことになります。
その際には贈与税(国税)を納付します。
その際には贈与税(国税)を納付します。
贈与税が新しく改正され、これまでよりも選択肢が増えました。新しい制度は、「相続」と「贈与」を一体で考えます。旧制度も選べ、どう使うかで損得が分かれます。
住宅取得資金贈与に関する特例の比較
| 旧制度【単純贈与】 | 住宅ローン契約書 | |
|---|---|---|
| 非課税枠 | 非課税限度額550万円 1,500万円までは贈与税軽減 ※平成17年末まで |
3,500万円(累計) ※平成19年末まで |
| 贈与する人 | 親・祖父母(年齢制限なし) | 親(年齢制限なし) |
| 贈与される人 | 子・孫(年齢制限なし) | 子(年齢制限なし) |
| 贈与される人の制限 | 合計所得 1,200万円以下 | なし |
| 条件 |
・自己居住用家屋取得 ・新築または中古住宅 (木造建築築後20年以内・ 耐火建築物築後25年以内) ・規模50m²以上 ・一定の増改築 ・1,000万円以上 |
・自己居住用家屋取得 ・新築または中古住宅 (木造建築築後20年以内・ 耐火建築物築後25年以内) ・規模50m²以上 ・一定の増改築 ・100万円以上 |
| 利用回数 | 生涯に1回限り | 何回でも可 |
| 申告 | 必要 | 必要 |
TAX
4
不動産取得税
住宅の新・増・改築、土地建物の購入、贈与、交換などで不動産を取得した際に、一度だけ納付する都道府県税です。
贈与税が新しく改正され、これまでよりも選択肢が増えました。新しい制度は、「相続」と「贈与」を一体で考えます。旧制度も選べ、どう使うかで損得が分かれます。
不動産取得税の計算方法は
住宅の新築、新築住宅購入、増改築の場合
| 建 物 | 建物の固定資産税評価額×3% 【特例措置】 (建物の固定資産税評価額-特別控除額1,200万円)×3% |
|---|
中古住宅購入の場合
| 建 物 |
建物の固定資産税評価額×3%
【特例措置】
(建物の固定資産税評価額-特別控除額)×3%
※下表の「控除額表」を参照してください。
|
|---|
住宅用土地の場合
| 建 物 | 土地の固定資産税評価額×1/2×3%=A 【特例措置】 A-税額控除額(※) ※税額控除は次のいずれか多い額になります。 ・土地の1m²あたりの固定資産税評価額×1/2×住宅の床面積の2倍(上限200m²まで)×3% ・45,000円 |
|---|
【特例措置】の要件
- (建物) 次の要件のすべてにあてはまる場合に適用されます。
- ・床面積が、50m²以上240m²以下(登記簿面積)
- ・中古住宅の場合は、新築後20年以内(耐火構造は25年以内)に建築された住宅であること。
- ・中古住宅の場合は、かつて人の居住用として使われたことがあり、個人が自己居住用として取得した住宅であること。
- ・自ら居住するための住宅であること
- ・新築または取得後1年以内の登記であること
- (土地) 次の要件のいずれかにあてはまる場合に適用されます。
- ・土地購入の日から3年以内に、その土地に住宅を新築した場合。
- ・新築または中古住宅(マンションを含む)を土地付きで購入した場合。
- ・住宅を新築し、新築後1年以内にその土地を購入した場合。
- ・中古住宅を購入し、その後1年以内にその土地も購入した場合。
- ・土地購入の日から1年以内に中古住宅を購入した場合。
TAX
5
固定資産税
土地・家屋の保有について課せられる市町村税です。
毎年1月1日現在で固定資産課税台帳に所有者として登録されている人に課税されます。
毎年1月1日現在で固定資産課税台帳に所有者として登録されている人に課税されます。
固定資産税の計算方法は以下のとおりです
課税標準×1.4%(税率) = 固定資産税
課税標準は、固定資産課税台帳に登録されている価格(固定資産税評価額)となっています。ただし、税率は地方税法によって1.4%~2.1%の範囲で各市町村が条例で設定することができますので、全国一律ではありません。毎年度、年4回に分けて納付します。
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地は、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けられ、それぞれ次のような税負担の軽減が図られています(ただし、家屋の床面積の10倍まで)。
- a) 小規模住宅用地
- 住宅1戸あたり「200m²」以下の部分については、固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の1を課税標準とします。
- b) 一般住宅用地
- 住宅1戸あたり「200m²」を超える住宅用地は、200m²までの部分を小規模住宅用地とし、200m²を超える部分については、固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1を課税標準とします。
新築住宅の税額軽減措置
下記の要件に該当する新築住宅は、当初3年度間(3階以上の新築中高層耐火住宅は5年度間)120m²までの部分の税額の2分の1が軽減されます。
| 床面積要件 | 居住部分の床面積が50m²以上280m²以下であること |
|---|---|
| 居住割合要件 | 併用住宅の場合、居住部分の割合が2分の1以上であること |
宅地にかかる税負担の調整措置
土地の固定資産税は評価替えに伴う税負担の急激な増加を緩和し、なだらかな税負担増とするため、負担調整措置が取られています。
TAX
6
都市計画税
市街化区域をもつ市町村が都市計画事業、土地区画整理事業のために必要な経費に充当するために課税する市町村税です。
市街化区域内の土地および家屋が対象となります。
市街化区域内の土地および家屋が対象となります。
都市計画税の計算方法は以下のとおりです。
課税標準×税率 = 都市計画税
課税標準は、固定資産課税台帳に登録されている価格(固定資産税評価額)となっています。 ただし、税率は0.3%を上限として各市町村が条例で設定することができますので、標準税率は規定されていません。また、毎年度、年4回に分けて納付します。
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地については、固定資産税と同様に課税標準を減額する特例があり、小規模住宅用地は3分の1、一般住宅用地は3分の2になります。
※ 小規模住宅用地、一般住宅用地の詳細は『5.固定資産税』を参照してください。
宅地にかかる税負担の調整措置
下記の要件に該当する新築住宅は、当初3年度間(3階以上の新築中高層耐火住宅は5年度間)120m²までの部分の税額の2分の1が軽減されます。
宅地にかかる税負担の調整措置
土地の固定資産税は評価替えに伴う税負担の急激な増加を緩和し、なだらかな税負担増とするため、負担調整措置が取られています。
TAX
7
すまいの税金に関する情報
あらゆる税金に関する質問を受けています。すまいに関する回答も多数あります。
住宅の税金に関するページです。住宅に係わる諸々の税金(相続等を含む)について、簡潔明瞭に整理された解説となっています。